要点:YMYL(医療・金融・法律・安全等)でSoraを使う際の「安全性・E-E-A-T・法規対応」を具体的なチェックリストで解説します。
YMYL分野でSoraを安全に使う 主な3点
- AI動画は「視覚補助」に限定し、効果の断定・誇張は避ける
- E-E-A-T確保:監修者明記/AI生成の開示/出典の提示と人手検証
- 法規確認:著作権・薬機法・景表法・肖像権を公開前に必ず点検
YMYL分野とAI動画の決定的なリスク
YMYL分野において、AI動画(特にSoraのようなリアリティの高いもの)を利用する最大のリスクは、その「信憑性」と「誤解の誘発」にあります。
1. 誇張表現による誤情報の拡散
AIはプロンプトに従ってリアルな映像を生成しますが、その内容が科学的根拠や専門的な裏付けを欠いている場合(例:根拠のない健康効果を断定的に表現)、ユーザーに誤った認識を与え、健康被害や金銭的損失につながる可能性があります。これは、Googleが最も嫌う「悪質な誤情報」としてペナルティの対象となります。
2. 専門性・権威性の欠如(E-E-A-Tの崩壊)
YMYL分野では、動画の解説者が実在する専門家(医師、弁護士、金融アナリストなど)であること、そしてその情報が信頼できる情報源に基づいていることが必須です。AIが生成した架空の人物や説得力のある映像は、一見すると「専門家らしい」ですが、経験や権威の裏付けがないため、E-E-A-Tを決定的に損ないます。
3. ディープフェイクと倫理的な問題
Soraは実写と区別がつかないほどの映像を生成できるため、悪用された場合、誤った医療情報や金融アドバイスを実在の人物の映像と組み合わせて流布するリスク(ディープフェイク)があります。企業やメディアは、この倫理的な問題に対し、極めて高い透明性を求められます。
【チェックリスト1】AI動画コンテンツの安全性担保
生成したAI動画の内容が、倫理的かつ情報的に安全であることを確認するためのチェックリストです。
- 事実確認の徹底: 動画内の全ての情報(数値、病名、法律の条文など)は、必ず複数の一次情報源(公的機関、専門論文など)でクロスチェックし、間違いがないことを保証しているか。
- 断定表現の回避: 「~は絶対に治る」「~すれば必ず儲かる」など、効果や結果を断定する表現を動画内(テロップ、ナレーション)で使用していないか。
- 注意書きの挿入: 動画の冒頭や概要欄に、「これはAIによって生成されたイメージ映像であり、専門的なアドバイスに代わるものではありません」といった免責事項や注意書きを明確に表示しているか。
- 誇張表現の排除: 現実の医療行為や金融商品のリスクを不当に軽く見せるような、過度に楽観的なイメージ映像になっていないか。
【チェックリスト2】E-E-A-Tを損なわない透明性の確保
YMYLにおける信頼性(E-E-A-T)を確保しつつ、AI動画を活用するための透明性に関するチェックリストです。
- 著者・監修者の明記: 動画を公開するページや動画内テロップで、コンテンツの責任者(実在の専門家)を明確にし、その資格や経歴を信頼できる形で提示しているか。
- AI生成であることの開示: 動画がSoraなどのAIによって生成されたものであることを、動画内、概要欄、または公開ページで明確に開示しているか。(例:「本動画の一部映像はSoraを用いて生成されています」)
- 情報源の明示: 動画で言及している重要な事実やデータについて、その出典(参照した論文や統計)を動画の概要欄や記事の本文で具体的に明記しているか。
- 人間による検証工程の証明: AIが生成した映像やスクリプトを、専門家が監修・検証したというプロセスをサイト内で示し、透明性を高めているか。
【チェックリスト3】著作権・薬機法・景表法のリスク回避
YMYL分野では、一般的な著作権に加え、特に以下の法律に抵触しないよう細心の注意が必要です。
- 著作権侵害の回避: プロンプトに具体的な映画名、著名なアート作品、商標登録されたキャラクターを含めていないか。AI生成動画の著作権・商用利用ルールに従い、利用規約を遵守しているか。
- 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の遵守: 健康・医療に関する動画で、承認前の効果を謳う、または医薬品・化粧品ではないものに効果効能を断定する表現を使用していないか。
- 景品表示法(景表法)の遵守: 金融商品やサービスに関する動画で、根拠のない「お得さ」や「儲け話」を過度に強調し、消費者に誤解を与える表示をしていないか。(「優良誤認」や「有利誤認」の回避)
- 肖像権・パブリシティ権の回避: AIが生成した人物が、実在する著名人や専門家と誤認されるような映像になっていないか。
Sora利用における特有の注意点とプロンプト設計
Soraのような超高精度なAIモデルを利用する場合、映像のリアリティが高いからこそ、誤解を避けるためのプロンプト設計が重要になります。
1. 「抽象化」を意識したプロンプト
具体的な医療行為や金融取引の様子を忠実に再現させると、特定の個人や状況と結びつきやすく、トラブルの原因になりかねません。プロンプトでは、「具体的な治療法」ではなく「健康的な生活のイメージ」といった抽象的かつ概念的な映像を生成させるように誘導します。
2. 「イメージ映像」であることを強調
プロンプトに「Illustrative only (イメージとしてのみ)」や「Conceptual visualization」といった言葉を含めることで、AIが生成する映像が「ドキュメンタリーや事実の再現ではない」という意図を明確に込めます。これにより、後のリスク開示や免責事項の説得力が増します。
YMYL分野におけるAI動画活用のベストプラクティス
YMYL分野でAI動画を安全かつ効果的に活用するための最適な方法は、AIを「情報の提供者」ではなく、「視覚的な補助ツール」として使うことです。
- 活用領域の限定: AI動画は、「サービスの利用イメージ」や「顧客の抱える抽象的な不安の視覚化」など、事実関係を伴わないイメージ映像に限定する。
- ナレーションとテロップの優先: 動画のメッセージの核となる情報は、AI生成された映像ではなく、専門家によるナレーションや検証済みのテロップに任せる。
- 専門家による最終編集: AIが生成した映像に、監修者のロゴ、顔写真、または専門家自身の解説映像を必ず重ね合わせることで、E-E-A-Tを「人間の権威」によって補強する。
まとめ:信頼性を失わないための二重チェック
AI動画生成モデルSoraは強力なツールですが、YMYL分野での活用は「信頼性を失うこと」と常に隣り合わせです。AI動画の利用は、コンテンツの安全性、E-E-A-Tの透明性、法的なリスク回避という三つのチェックリストをクリアすることを絶対条件とすべきです。
AIが生成した映像はあくまで「素材」であり、その「意味づけ」と「責任」は、すべてコンテンツを公開する人間にあります。特にYMYL領域では、AI生成であることの開示と、専門家による二重チェックの徹底が、サイトの信頼性を守り、SEOペナルティを避けるための必須戦略となります。
無料配布:AI × SEO チェックリスト(PDF)
【検索に強く、読まれるサイト】をつくるための実践チェックリストです。
実務でそのまま使える全38項目を網羅しています。
※ 登録後は、AIを活用したSEOの最新Tipsもお届けします。
FAQ
Soraの映像を医療記事に使う最小限の安全ラインは?
事実に関わる主張は、映像ではなく監修者のナレーションとテロップで提示し、映像は概念説明やイメージに限定する。そして公開前に一次情報でクロスチェックし、AI生成の開示を添えます。
AI生成であることの開示はどこに書けば十分ですか?
動画内テロップ(冒頭数秒)・動画概要欄・記事本文の3箇所に記載すると実務上安心です。例:「本動画の一部映像はSoraで生成したイメージです」。
実写とAI映像の合成はYMYLで避けるべき?
誤認の恐れが高い演出(実在人物に医療効果を断定させる等)は避けるべきです。合成する場合も監修者の実名・肩書・出典を並置し、誇張表現を排し、免責を明示します。
監修者がいない場合は公開を見送るべき?
YMYLでは推奨は監修ありです。どうしても出す場合は、体験談やサービス紹介など事実検証を伴わない範囲に限定し、助言に当たる情報は掲載しない方針が安全です。
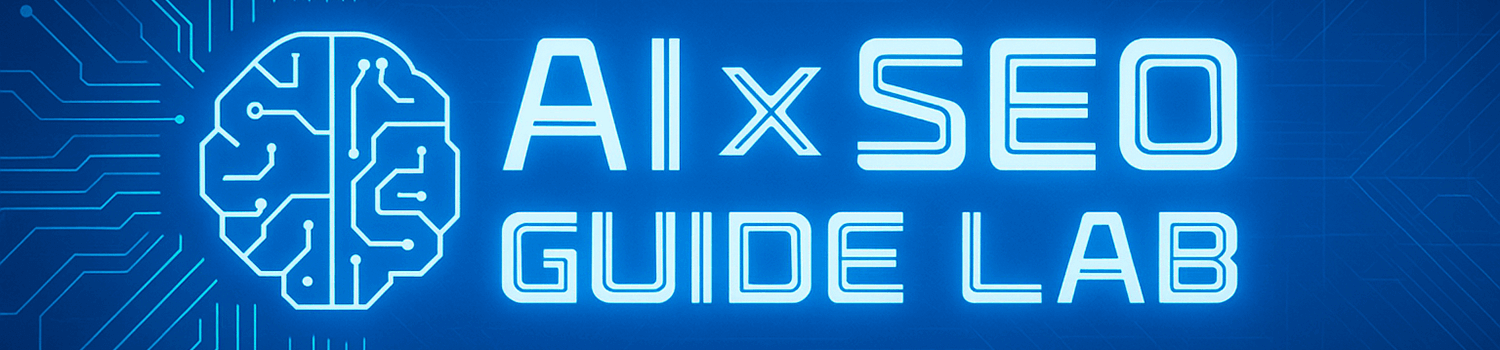


コメント