要点:Googleコアアップデートの狙いと流れを押さえつつ、AI記事が受ける影響と勝ち筋を整理しました。
AI記事は、Googleコアアップデートに影響ある?
- GoogleはAI使用自体を罰しないが、低品質量産は厳格に排除される。
- 評価低下の共通点はE-E-A-T不足・出典不備・UX劣化。
- 一次情報の注入と著者の権威提示、構造化とUX改善が変動に強い鍵。
Googleのコアアップデートは、検索エンジンのランキングアルゴリズムにおける大規模な変更であり、そのたびにWebサイトの検索順位は大きく変動します。特にAIライティングツールが普及して以降、「AIで生成した記事はアップデートでペナルティを受けるのではないか?」という懸念がWeb担当者の間で高まっています。結論から言えば、GoogleはAIの使用そのものを罰してはいませんが、アップデートはAI記事の品質の「穴」を容赦なく狙い撃ちします。
この記事では、Googleコアアップデートの歴史的背景とその目的を振り返りながら、AI記事がSEO観点で受ける影響を初心者にもわかりやすく詳細に解説します。過去のアップデートで順位が落ちたサイトの事例から、今後、どのようなAI活用サイトが評価を下げ、逆にどのようなサイトが評価を上げていくのかを徹底的に分析し、変動に強いコンテンツ戦略を構築するための指針を提供します。
Googleコアアップデートの目的と歴史
Googleコアアップデートは、ランキングの基盤となるアルゴリズムの大きな見直しです。その目的は一貫して、「ユーザーに最も有用で信頼できるコンテンツ」を提供することにあります。過去の主要なアップデートの多くは、特定の低品質な手法を排除するために実施されてきました。
歴史:品質評価の進化
- パンダアップデート(2011年~): 低品質・低付加価値のコンテンツ、コンテンツの重複を排除。
- フレッドアップデート(2017年): 収益化を目的とした広告過多のサイト、薄いコンテンツを対象。
- E-A-T重視のアップデート(2018年以降): 医療・金融などのYMYL(Your Money or Your Life)分野で、専門性・権威性・信頼性の低いサイトの評価を厳格化。
これらの歴史的経緯から、Googleは常に「量より質」「ユーザー第一主義」へと舵を切っており、AI時代のアップデートもこの基本原則から逸脱することはありません。
AI記事に関するアップデートの誤解と真実
AI記事に対するGoogleの姿勢について、誤解されがちな点を明確にしておきます。
誤解:「AIで書いた記事はすべてペナルティ対象になる」
これは誤りです。Googleは、AIをコンテンツ作成のためのツールとして認めており、AIが生成したという事実だけでペナルティの対象にはしません。重要なのは、その記事が「検索結果の操作」を目的としたスパム的な低品質コンテンツであるかどうかです。
真実:「AIによる低品質なコンテンツの乱造はペナルティ対象となる」
AIの効率性を悪用し、人間のチェックや独自の価値注入を伴わずに、キーワードだけを変えたような同質的で低付加価値な記事を大量に公開する行為は、「自動生成コンテンツ」というスパムポリシー違反と見なされます。コアアップデートは、このような「量産された低品質コンテンツ」の排除を主な目的の一つとしています。
コアアップデートの歴史的教訓:順位が落ちたサイトの特徴
過去のコアアップデート、特にE-A-Tが重視された2018年以降の変動で、評価が急落したサイトには共通の特徴が見られました。これらは、AI記事が陥りやすい弱点でもあります。
- 権威性の証明が不足している: 誰が書いたか不明確、または執筆者の専門性(資格、実績)がプロフィールのどこにも明記されていない。
- 裏付けのない断定的な表現: YMYL(特に健康・医療)分野で、公的機関の裏付けや医師の監修がない、断定的な治療法や健康情報を掲載している。
- 競合と内容が酷似している: 検索上位記事の内容を組み替えただけで、独自の調査や意見、経験が一切含まれていない「薄い」コンテンツ。
- 広告が過剰で、UXが悪い: ユーザーの疑問解決よりも、アフィリエイトリンクや広告収入を優先した構成になっており、記事の可読性が低い。
AI記事の最大のリスクは、これらの「低品質の特徴」を、意図せずとも簡単に再現・大量生産してしまうことにあります。
今後、評価が下がっていくAI活用サイトの特徴
AI時代に特化して、コアアップデートで評価を下げやすいサイトの傾向は以下の通りです。
1. AI丸投げによる「ジェネリックコンテンツ」
AIで生成した記事の初稿に対し、人間のリライトやファクトチェックが5%未満のサイト。内容は網羅的でも、競合サイトと見分けがつかない「ジェネリック(汎用的)な情報」のみで構成され、独自の価値がありません。
2. 意図的に経験(E)を排除したサイト
AIのハルシネーション(誤情報)を恐れるあまり、AIの出力のみに頼り、あえて「筆者の経験」「独自の分析」といった主観的なE-E-A-T要素を排除しているサイト。結果的に、Googleが最も評価したい「独自の情報」がなくなり、評価が低下します。
3. 不正確な引用や出典の記載
AIが生成した「~によると」といった出典を人間が確認せず、情報源のないデータや統計をあたかも事実であるかのように掲載しているサイト。これは信頼性(Trustworthiness)の欠如と見なされます。
今後、評価が上がっていくAI活用サイトの戦略
コアアップデートの変動で順位を伸ばすのは、AIを「効率化」ではなく「品質の向上」のために活用しているサイトです。キーワードは「ハイブリッド戦略」です。
1. 独自の一次情報(経験)を核にする
AIを「リサーチと構成案の叩き台」として利用し、記事の核となる最も重要なセクション(例:筆者の失敗談、独自の実験データ、顧客インタビュー)は、必ず人間が一から執筆します。これにより、競合AI記事が真似できない独自性(E-E-A-Tの「E」)を確立します。
2. 権威性(A)を視覚的に証明する
AI記事であっても、記事の著者を特定し、その人物の「専門性(Expertise)」を証明する具体的な実績(資格、受賞歴、業界歴)を著者プロフィールに詳細に記述します。YMYL分野であれば、必ず専門家(医師、弁護士など)に監修を依頼し、その事実を明記します。
3. 構造化とUXの徹底的な改善
AIで生成した文章をそのままにせず、箇条書き、表、図解を多用して可読性を高めます。特に、読者の疑問に直結する結論は簡潔に断言し、ストレスなく情報を得られるようUXを最適化します。これは、Googleがユーザーシグナルを評価する際に非常に重要です。
変動に強いコンテンツの核:E-E-A-Tの証明
AI時代においても、コアアップデートで順位を守り、伸ばすための究極の対策は、Googleが掲げるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を徹底的に証明することに尽きます。
| E-E-A-T要素 | AI記事で証明するための具体的行動 |
|---|---|
| 経験 (Experience) | 記事に「筆者が〇〇を試した」「私の失敗談」といった独自の一次情報を30%以上注入する。 |
| 専門性 (Expertise) | AIが出せない専門用語の背景知識や、高度な考察を人間が追記・リライトする。 |
| 権威性 (Authoritativeness) | 記事の著者を明記し、業界での実績や受賞歴をプロフィールに詳細に記述する。 |
| 信頼性 (Trustworthiness) | すべての数値やデータについて、公的機関への出典(URL)を明記し、AI生成情報のファクトチェックを徹底する。 |
まとめ:AIは手段、品質がすべて
GoogleコアアップデートとAI記事の関係は、「AIは低品質なコンテンツを量産するリスクを高めたが、高品質なコンテンツ制作を加速させる可能性も持っている」という二律背反の側面を持っています。アップデートが来るたびに評価が下がるのは、AIに「品質保証」の責任を丸投げし、独自性や信頼性の注入を怠ったサイトです。
AIを単なるツールとして割り切り、人間のリソースをE-E-A-Tの注入と品質チェックという「価値の創造」に集中させること。このハイブリッド戦略こそが、AI時代におけるGoogleコアアップデートの変動を乗り越え、検索結果のトップを維持するための唯一の答えとなります。
無料配布:AI × SEO チェックリスト(PDF)
【検索に強く、読まれるサイト】をつくるための実践チェックリストです。
実務でそのまま使える全38項目を網羅しています。
※ 登録後は、AIを活用したSEOの最新Tipsもお届けします。
FAQ
AIで書いたことは明記するべきですか?
必須ではありませんが、執筆体制や監修体制を透明化し、著者情報と一次情報の提示で信頼性を担保してください。
アップデート直後にやるべき確認は?
落ちたURLの共通点(E-E-A-Tや出典の弱さ、UXの阻害要因)を洗い出し、重要ページから順に改善します。
AI記事のファクトチェックはどこまで必要?
数値・法律・医療などYMYLは一次情報で必ず裏取り。一般トピックも主要主張は出典を明記しましょう。
リライトと新規作成、どちらを優先すべき?
変動影響の大きい上位狙いページはリライトを優先。流入余地の大きいクラスター欠損は新規で補完します。
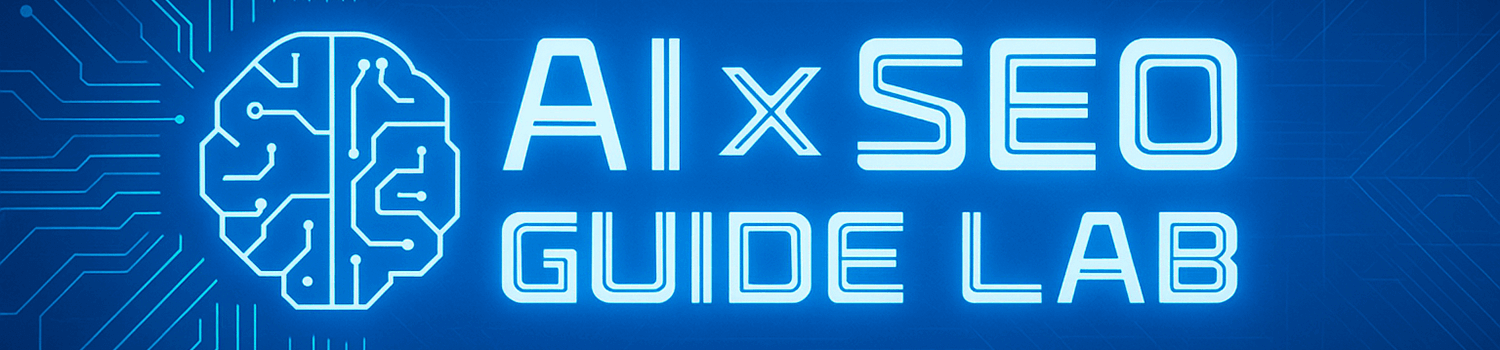
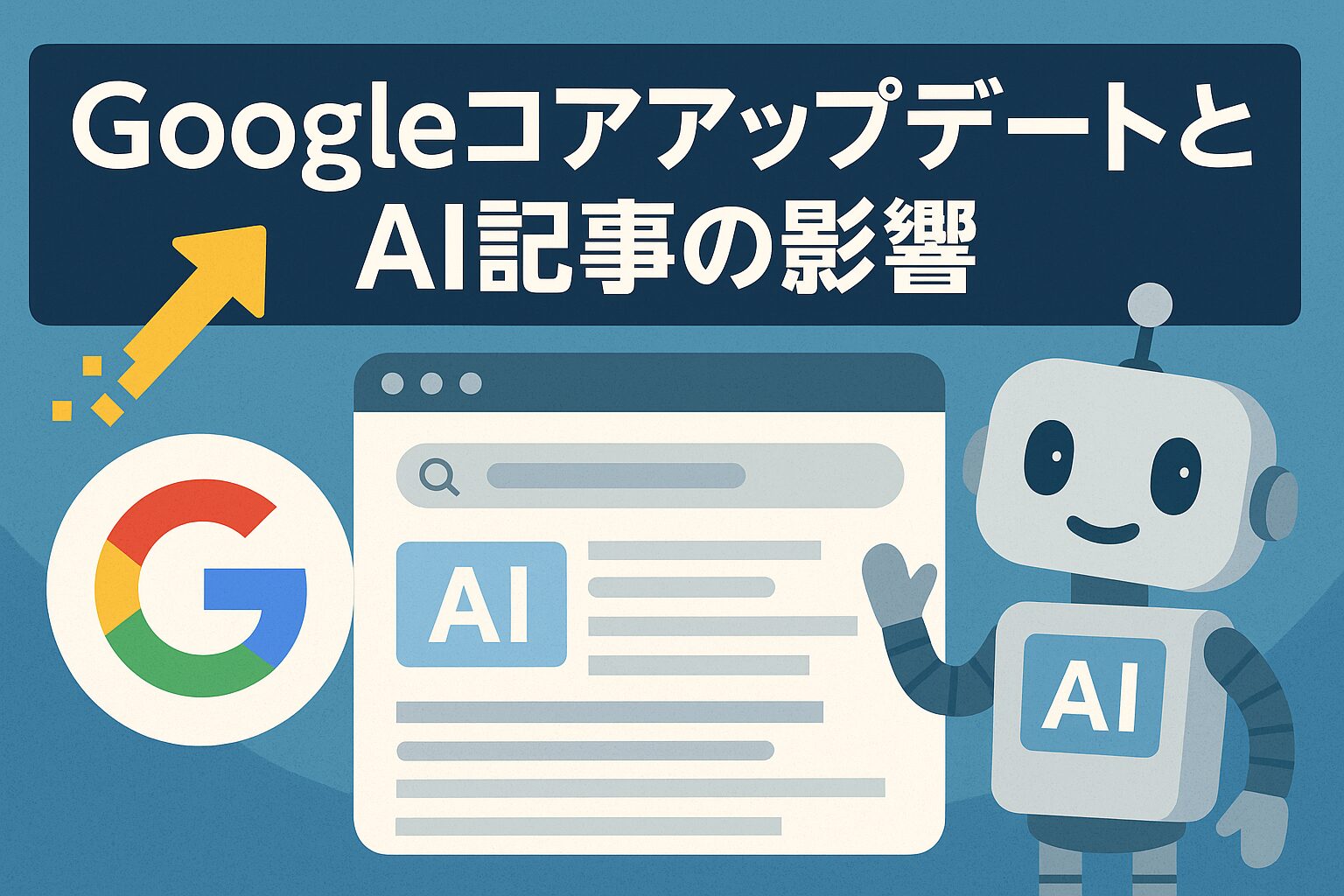

コメント